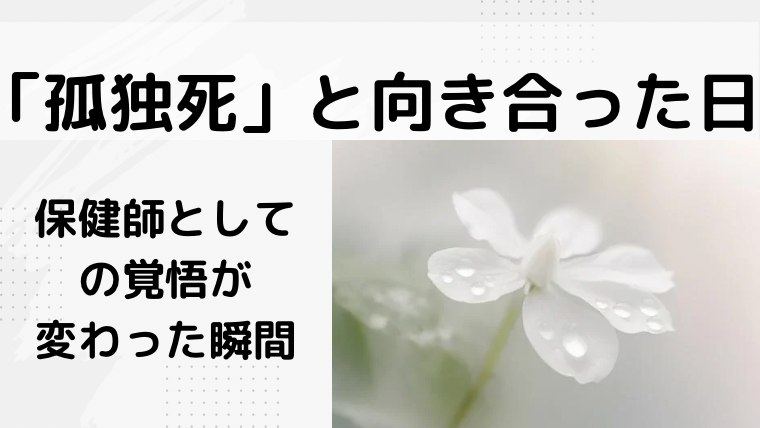地元の中核市で保健師として働いていた時のこと。
担当は高齢者保健福祉。介護予防や要介護認定調査、地域包括支援センターの後方支援、認知症サポーター養成、高齢者虐待対応など——とにかく高齢者に関わる業務全般を担っていました。
もともと「保健師は専門職」という意識が強く、窓口での相談業務や訪問業務が中心だと思っていました。けれど、行政に入ると、まるで「なんでも屋」みたい。次第に、考え方をシフトせざるを得ないと感じていました。
そんな矢先、ある出来事が起こりました。
「死後、数日が経過しています」——突然の孤独死の知らせ
秋の気配が漂い始めたものの、まだ暑さが残るある日。
「最近、あの人の姿を見かけない」「家のあたりから、変な匂いがする」
近隣住民の通報で発見されたのは、私の担当地区に住む独居高齢者の方でした。生活保護は受けておらず、介護保険のサービスも利用していない。家族の情報もなく、年金で暮らしていたと思われましたが、生前の記録は何もありませんでした。
そして私に下された指示は、「家宅捜索」。
「健康を支える保健師」として働くはずだったのに、まさか人の死後にその人の家を捜索することになるとは——。
衝撃でした。
もう一人の職員とともに、年賀状の束をめくり、親戚らしき人に連絡を取りました。
「遠方のため行けませんが、遺骨は郵送してください」
電話越しにそう告げられた時、胸の奥がぎゅっと締めつけられました。
「生前、お会いしたこともない方の火葬」
火葬場へ向かう車の中、正直とても心の中は複雑でした。
火葬が始まり、生活支援課の職員は今後の費用や手続きを話し合っていました。
私は、一人、少し離れた場所で泣きました。
隣の火葬場では、家族や親族に見守られながら、涙の別れが交わされている。一方、この方は、、、名前を呼ぶ人もなく、見ず知らずの一行政職員の手によって、静かに骨壷へと納められていく。
「この人は、どんな人生を歩んできたんだろう」
「友人はいたのだろうか」
「最期の時、苦しくなかっただろうか」
言葉にならない感情が押し寄せました。
その日の帰り道の記憶は、ほとんどありません。20代前半の私にとって、あまりに重く、整理しきれない出来事でした。
「孤独死をなくすために、私ができることは?」
数日後、仲の良い先輩と残業していた時、この出来事を打ち明けました。
しばらく沈黙が続いた後、先輩がふと呟きました。
「孤独死って、どうやったら無くせるんだろうね」
その瞬間、ハッとしました。
私の担当地区の高齢化率は 42%。地域住民も、「孤独死をどう防ぐか」が課題だと感じていました。
この方のように、誰にも気づかれず、ひっそりと人生を終える人を少しでも減らしたい。
私ができることは、きっとあるはずだ。
そう気づいたのです。
この出来事をきっかけに、私が担当地区で取り組んだこと——
それは、また次回お伝えしようと思います。
最後に——「死」と向き合うことの意味
人は、誰かの死と向き合うことで、何かを学びます。
そして、その学びを行動に変え、次の「生」へとつなげていくことができるのではないか。
この方の死を無駄にしないために。
そして、同じような孤独死を少しでも減らすために。
明日も、良い一日になりますように。にこにこで行こう。